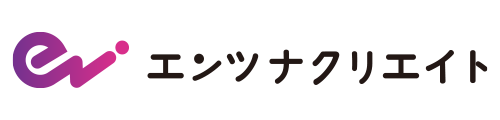属AI化とは何か?

~ChatGPT時代の新・属人化問題と、その処方箋~

【はじめに】属人化の次に来るもの
「この作業は〇〇さんしかできない」
「そのノウハウは△△さんの頭の中にあるだけ」
こうした“属人化”の課題は、多くの中小企業にとって身近な問題でした。
そして今、AI時代に突入した私たちの前に現れつつあるのが、「属AI化」という新たな課題です。
属AI化とは、AIツールの利用が特定の個人に偏ることで、以下の様な状態を指します。
- 活用方法やプロンプトがブラックボックス化
- 他の人が業務を引き継げない
- 結果としてAIが「属人化」してしまう状態
つまり、AIを活用しているにもかかわらず、結果的に業務が特定の個人に依存してしまう状態です。
なぜこの問題が今注目されるのか?
それは、ChatGPTなどの登場により、AIが特別な専門家だけのものではなく、誰でも使える時代になったからです。
AIはすでに「使う前提」に置かれており、特に中小企業では「気づいたときには既に競合が導入していた」という状況が起きやすくなっています。
本記事では、この「属AI化」という現象をひも解きながら、
具体的にどのようなリスクがあり、どうすれば防げるのかを説明しています。
属人化の時代から、属AI化の時代へ

属人化とは何だったか
属人化とは、業務や知識が特定の個人に依存し、その人でなければ遂行できない状態を指します。
この状態では担当者が不在になると業務が滞り、品質低下や納期遅延のリスクが高まります。
また、引き継ぎが困難で組織全体の生産性低下を招き、人材育成や業務改善も進みにくくなります。
そのため、標準化やマニュアル化、情報共有による属人化の解消が重要です。
無料ブログ終了のトラウマに似ている
かつて個人ブログサービスが終了したとき、コンテンツが消え、多くの人が「残しておけばよかった」と後悔しました。
同じように、AIの活用方法が「個人の中にしかない」状態は、非常に危ういのです。
属AI化の時代とは
AIの導入が個人主導で進む
- ChatGPTや画像生成AIなどを、まずは興味のある社員が個人的に使い始める。
- 部署や組織としてのルールや共有がなく、利用が断片的。
成果が個人に閉じる
- プロンプト(指示文)や利用ノウハウが担当者のメモ帳や頭の中だけに存在。
- 他のメンバーは同じ結果を再現できず、AI活用が「属人化」した状態になる。
リスクが顕在化する
- 退職・異動でAI活用が止まる
- 無料アカウントや個人環境に依存し、ツール停止や仕様変更で業務に影響
- AI活用の「資産化」ができておらず、組織としてのAIレベルが上がらない
属AI化の現象:気づかない落とし穴

こんなこと、起きていませんか?
- 「〇〇さんだけがAIを使っている」
- 「ChatGPTのプロンプトは個人のメモ帳にだけ保存されている」
- 「他の人が同じことをやろうとしても、再現できない」
属AI化が起きるメカニズム
担当者が個人的にChatGPTなどを使い始める
組織的活用にはつながらない
個人の工夫・プロンプトで成果が出始める
他者が真似できない
AIへの依存が深まり、個人しか触れなくなる
担当者がいなくなると業務が止まる
属AI化の実例
プロンプト管理が個人任せ
ある担当者だけが業務に必要なAIプロンプト(指示文)を作成・管理し、その情報が退職時に個人のメモ帳やクラウドにしか残っていない。
結果:他の人が同じ精度でAIを活用できず、業務がストップ。
AIサービス終了や仕様変更に伴う「資産の蒸発」
あるAIツールに業務を完全依存していたが、突然のサービス終了や仕様変更で環境を失い、再構築に時間とコストが発生。
例えば:ChatGPTに依存 → サービス終了 → 代わりのツールがない
結果:特定のサービス・環境に過剰依存し、柔軟な切り替えができない。
個人アカウントのみで使用
無料アカウントの凍結により、履歴に保存していたプロンプトがすべて消失。
結果:プロンプトや設定が個人アカウントのみで組織資産になっていない。
属AI化が業務にもたらすリスク

属AI化は、従来の属人化よりも影響範囲が広く、発生が急速です。
例えば、担当者が突然退職すれば、プロンプトやノウハウだけでなく、AIツールの設定や履歴までもが一気に失われます。
また、外部サービスに依存していた場合、仕様変更や停止が起こると業務全体が止まってしまうリスクもあります。
これは「個人依存」だけでなく「外部依存」による二重のリスクです。
【解決策】仕組みとしてのAI活用へ

プロンプトの構造化
誰でも閲覧・利用できる状態にする。
社内のクラウドツール(Googleドキュメントなど)にまとめ共有し、ナレッジを蓄積します。

再セットアップ可能な環境整備
AIサービスのAPIキーや設定(モデル選択、接続方法、権限管理)を個人アカウントでなく管理者アカウントで一元管理。環境が壊れた時でもすぐに再構築できるよう、設定手順書やインフラ構成を残しておく。

属AI化診断の導入
属人化の度合いとAI活用の度合いをスコア化(業務棚卸・AI活用率・担当者依存度)。
定期的に進捗をチェックし、改善点を明確化。
【まとめ】
属AI化は進む。だからこそ「仕組み化」が必要
属AI化は放置すると「担当者の退職」「サービス停止」などで業務が即ストップする場面を引き起こします。
だからこそ、AI活用は「誰でも使える仕組み」にしておくことが大切です。
属AI化の正体
AI活用が特定の個人や環境に依存し、組織全体で再現できない状態。
放置すると起きること
- 担当者がいなくなるとAI活用が止まる
- サービス終了や仕様変更で業務が混乱
- ノウハウが社内資産として残らない
解決のポイント
- プロンプトを共有・標準化する
- AI環境を管理者アカウントで一元管理
- 属AI化診断で進行度を可視化
【おわりに】
AIは「引き継げる」ものにしよう

属AI化の正体は、AI活用が特定の個人や環境に依存し、組織全体で再現できない状態です。
放置すると、担当者の退職や外部サービスの変更一つで業務が止まり、ノウハウが社内資産として残らないという事態になります。
解決の第一歩は、プロンプトや設定を共有・標準化し、環境を組織として管理すること。
まずは身近な業務から、小さく試して「引き継げるAI活用」を始めましょう。
あなたの会社のAI活用、もし担当者が辞めたら引き継げますか?
もし、アカウントが停止されたら、代替できますか?
エンツナクリエイトでは、
- 属AI化の診断
- 再設計支援
- チームで使えるAI環境構築
といった「AIを組織の武器にする仕組みづくり」をサポートしています。